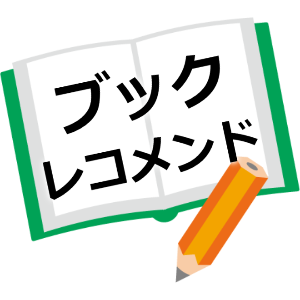はじめに:「小説を書いてみたい」と思う人へ
小説を書いてみたい。でも、どうやって物語を作ればいいのか分からない。
そんな思いを抱えているあなたへ。
物語を書くことは、決して「特別な人」だけのものではない。
物語の世界は、あなたの中にすでにある。
あとは、それを言葉にするだけ。
さあ、一緒に「書く」という冒険を始めよう。
書籍の基本情報
| タイトル | : | クリエイターのための物語創作ノート |
| 発行日 | : | 2022年8月1日 |
| 著者 | : | 秀島 迅 |
| 発行所 | : | 日本文芸社 |
| 詳細 | : | クリエイターのための物語創作ノート |
主要なポイント・学び
創作意欲に目覚めたあなたへ――物語を書くためのコツや技術が数多く存在する。
それらテクニックをマスターして実践すれば、思い描いたイメージを具現化できる。
物語創作のテクニック
物語創作の第1歩――物語の創作で一番大切なこと。
それは、物語のきっかけを頭の中で自由にイメージすること。
エンディングでもいいし、クライマックスのシーンでもいい。
たった1行の台詞だっていい。
それが物語創作の扉を開く鍵となる。
そのシーンや台詞には、物語の世界観が凝縮されている。
そして、そこには必ず主人公がいる。
さらに深く想像をめぐらせてみよう。
周囲には他のキャラクターも存在している。
登場人物は自然と生まれていく。
そうすれば、物語の大枠が見えてくる。
物語の3つの構成要素――物語は、次の3つの要素で構成される。
- ジャンル:物語の様式や題材
- テーマ:物語を通して伝えたいメッセージ
- 設定:物語の舞台や登場人物の関係性の定義
ジャンルを決める――ジャンルの選択方法は2つある。
「得意」と「人気」は違う。
好きなジャンルを選べば、自分が書きやすいというメリットがある。
しかし、得意ジャンルばかり選ぶと他のジャンルが書けなくなり、やがて行き詰る。
人気の高いジャンルを選べば、エンタメ市場で高評価を得られる可能性がある。
しかし、そのジャンルが自分の嗜好と異なれば予備知識の勉強や取材が必要となる。
テーマを決める――テーマは読み手に共感されるものでなければならない。
書き手には、社会全体や世代別の問題、課題を見抜く洞察力・観察力が求められる。
物語の主人公は、テーマを背負い、成長、進化、問題解決するように動く。
そのため物語の導入部の主人公は、大切な「何か」を喪失している。
物語を通して主人公は右肩上がりで成長し、結末で大切な「何か」を獲得する。
ただし、ご都合主義になってはならない。
設定を決める――設定はキャラクターとテーマに密接に関係する。
大多数の理解・共感を得やすいものにするのがポイント。
設定は、空想上の家に似ている。
設定とは、登場人物の行動を即し、あるいは制限するもの。
家が大きければ、たくさんの人が集まり壮大な物語になる。
家が小さければ、身近な少数の人が集まる小規模な物語になる。
設定が曖昧だと物語が成立しなくなる。
ストーリーを組み立てる
ストーリーの基本――起承転結。
- 起:主人公の喪失状態で始まる
- 承:事件発生、ピンチ到来
- 転:山場、意外な方向へ
- 結:主人公の状態回復、希望
山あり谷あり。一本道ではドラマは成立しない。
ストーリーのゴールとは、テーマの達成。
ストーリーライン――それは物語の主なイベントを時系列で整理したもの。
ジャンル、テーマ、設定が決まったら具体的なストーリーラインを書く。
ストーリーには、鉄板のパターンがある。
過去の物語をモチーフにして、オリジナリティを加えていく。
あらすじ――それはストーリーラインに肉付けして内容を膨らませたもの。
オリジナリティも出していく。
絶対入れたい要素は、この段階で付け加えておく。
あらすじは、設計図。綿密に作り込む必要はない。
キャラクター設定
登場人物全員が重要――物語が面白くなるかは、登場人物にかかっている。
なぜなら登場人物は、テーマに連動して書き手が伝えたい思いを体現する存在だからだ。
物語におけるキャラクターの役割には、4つの配役がある。
執筆前に全員分のリストを作成しよう。
細かな部分まで作り込む綿密な準備が必要である。
リストに、登場人物のイメージに近い俳優の画像を添付するのがおすすめ。
視覚化することで描きやすくなる。
魅力的なキャラクター――それは面白い物語の必須条件。
キャラクターの性格、長所・短所、強み・弱みに対する書き手の深い理解が重要。
そのうえで、魅力的なキャラクターを描くためのノウハウがある。
キャラ立ち――そのためには行動原理が必要。
行動原理とは行動の根本的な動機となる本能・欲求・願望・信条・価値観。
魅力的なキャラクターには行動原理が不可欠。
例
読み手の感情を揺さぶるには、キャラクターの行動原理に共感してもらう必要がある。
ストーリーを牽引する主人公は、行動原理を明確にして動き続けなければならない。
主人公の目的――書き手は常に主人公の目的を念頭に置かなければならない。
主人公の行動は終始一貫して目的に集約される。
そして目的が達成された瞬間、読み手の満足感が最高潮に達するよう描く。
主人公の確固たる目的意識があれば、キャラクターが勝手に動き始める。
仲間や協力者のキャラクターを動かしやすくなる。
主人公を邪魔する敵にも行動理由ができる。
キャラクターの性格――性格を与えることで各キャラクターの位置づけを明確にできる。
キャラクター同士の会話が描きやすくなり、展開のスピード感を高めることができる。
また、読み手が感情移入しやすくなる。
性格には、良い状態と悪い状態がある。
キャラクターは良い状態、悪い状態でそれぞれどのような行動に出るのか。
感情の起伏を突き詰め、掘り下げて描かなければならない。
性格を描写するテクニック
読み手の共感を呼ぶ――キャラクターに強さと弱さの2つの顔を持たせる。
弱点やコンプレックスを持たせ、それらを克服したとき、読み手に大きなカタルシスを生む。
ただし、あからさまで、取ってつけたような弱点にしてはいけない。
世界観の作り方
世界観――それは登場人物を取り囲む世界のあり方。
大雑把なでたらめの設定では、読み手は納得しない。
大前提は「自分の力量で描ける世界観」を選択すること。
文化――それはテーマと密接に関わる。
題材とするモチーフには必ず文化が含まれる。
どんな文化をどれだけ深く描くかがキーポイント。
文化を描くプロセスは、そこに関わり生きる人たちを描くことにつながる。
文化を描き切るには、専門知識や十分な取材が必要となる。
プロットを作る
プロット――それは物語がどのように進行するかを示す地図。
プロットを描く目的は、2つある。
プロットとは、論理的ストーリーラインより詳細に実際の執筆の流れの通りに要点を簡潔に書いた起承転結の構成案。
ストーリーの「起」と「結」を1本の線でつなげる。
起と結が具体的になれば承と転は難しくない。
キャラクターの心情やテーマに関わる重要ポイントを描く。
プロットのテンプレート
プロット作りで外してはいけない3つのこと
フラグ――それは伏線という意味で、必須の描写テクニック。
読み手に気づかれないよう、「起」か「承」に埋め込む。
プロットの段階でフラグを複数個考える。
執筆中に思い付きで加えると読み手を混乱させるだけで終わる。
王道――読み手の希望と願望に応える展開でエンディングを迎える物語の在り方。
王道の物語を成立させるためには、3つの条件がある。
構成基盤を参考にする――物語は次の13項目の構成基盤に分類される。
この構成を意識してプロットを組み立てる。
- オープニング
- 状況説明
- 主人公登場
- テーマの提示
- 葛藤
- 努力
- プロットポイント(物語の転換期①)
- 危機
- 暗闇
- 悪戦苦闘
- プロットポイント(物語の転換期②)
- 解決
- エンディング
①-④:起、⑤-⑦:承、⑧-⑩:転、⑪-⑬:結
物語の作り方
面白い物語の3つの特徴
ファーストシーン――冒頭の4ページで読み手を惹きつけなければアウト。
読み手は、冒頭で面白いかつまらないかの決断を下す。
大事なことは「とにかくストーリーを動かす」こと。
ファーストシーンで押さえるべきポイントは、次の6つ。
「Save The Cat!」とは「ピンチに陥った猫を危機一髪のところで救うエピソードを序盤に入れよ」という法則のこと。
多くの読み手はプロローグが嫌い。
それでもプロローグから始めるなら、衝撃的な展開を予感させる文章構成でなければならない。
登場人物の視点での描写――あらゆる場面は登場人物の誰かの視点で語られる。
例:主人公「僕」の視点で語る場合
書きながら誰から見た状況なのか、慎重に考えよう。
物語を通して主体となる登場人物の違いで、視点のタイプは2つある。
1人称1視点――初めて物語を書くとき、取り組みやすい。
現代が舞台の身近な世界観で主人公の成長を描くドラマに適している。
1人称1視点で物語を最初から最後まで書き通す場合、主人公の行動範囲を広げ、多くの登場人物とのかかわりを持たせるよう意識的に書く。
3人称多視点――群像劇、ミステリー、サスペンスなど大きな世界観の物語に適している。
Aさん視点になったりBさん視点になったりCさん視点になったり切り替わり物語が進む。
他視点で物語を進めることができ、チャプターごとに視点人物を変えることができる。
書き手はつねに1歩引いた場所から主人公をはじめとする登場人物を俯瞰して執筆する。
描写の作り方
物語の2つの描写
背景描写――登場人物がいる場所での天候や時間帯や空間の状態を描いたもの。
視点のキャラクターが何を見て、どういう状況にいるかを明確にする。
物語の進行と関わる核になる描写に留める。
物語の展開の暗示を含ませることで読み手の感情移入度をアップさせることができる。
人物描写――人物描写には、次の2つがある。
台詞と描写の割合――5:5が目安。
文章は、基本的に次の3つで構成される。
- 描写
時間軸を一時停止またはとても緩やかにして、シーンの状況を説明する。
- 台詞
物語が展開している現実世界と同様の時間の流れ。
もっとも物語に臨場感を与える。
- 説明
時の経過を早めて、展開を先へと勧め、新たなシーンに変える。
「説明」はとにかく最小限に抑える。
また、台詞のみ、または描写のみで5行以上書かない。
過去描写――時系列の流れだけに沿って進行すると物語が単調になってしまう。
過去の出来事を掘り起こせばストーリーに深みや広がりを与えることができる。
ただ過去に遡るだけでは効果はない。
過去の点と点が1本の線でつながり、現在軸に合流する工夫を施すことが大事。
過去描写には、気をつけるべきことが2つある。
情景描写――それを眺めている登場人物の心が反映されたもの。
見た目以上の「何か」を含有させることで、その後の物語の展開に色を添える。
ただし、感情を盛り込む場合は不自然にならないように留意して描く。
エンディングシーンのポイント――一番重要なのは、描き過ぎないこと。
エンディングシーンで何より大切なのは「余韻」。
読み手に何かを考えさせる余地を残しておくと読後に豊かな気持ちになれる。
物語のエンディングは、大きく2つに分類される。
- 閉じた結末(クローズドエンド)
すべてが解決して終結し、もう続きはありえない形式。
- 開かれた結末(オープンエンド)
事件のすべては解決せず謎が残るなど、余地や余韻を残す。
最終的な解釈を読み手に任せて終わる形式。
双方の特徴を理解し、どちらの結末で描くか選択する。
まとめ・感想
本書の技術は、数々の人気作品の中で使われている。
たとえば、吾峠呼世晴先生の『鬼滅の刃』で考えてみる。
『鬼滅の刃』は現在『鬼滅の刃 無限城編』が全国の映画館で上映されている人気作品だ。
本書の技術を知ったうえで『鬼滅の刃』を振り返ると、ストーリーもキャラクターもとても考えて作り込まれていることがわかる。
ためしに単行本第1巻の流れをプロットの構成基盤13項目にリバースエンジニアリングしてみるとだいたい次のようになると思う。
主人公「竈門炭治郎」は、物語の冒頭で人喰い鬼に家族を殺されてしまう。
さらに、ひとり生き残った妹「竈門禰豆子」も鬼にされてしまうという「喪失」を経験する。
大切な家族のすべては失うまいと、禰豆子を人間に戻すことを「目的」に炭治郎は旅立つ。
突如襲ってくる鬼殺の剣士「冨岡義勇」から禰豆子を守るため、頭を下げ助けを乞うか、立ち向かうかの炭治郎の「葛藤」。
戦うことを選んだ炭治郎は義勇に倒され、兄を庇い戦おうとする鬼の禰豆子。
ここで物語が大きく動き出す「第一の転換期」を経る。
義勇から紹介された「鱗滝左近次」に会うべき向かう道中、鬼に襲われながら進む「危険」。
鬼殺の剣士になるための修行では「自分にはできない」試練を課せられる「暗闇」。
鬼殺隊に入隊するための最終戦別での「悪戦苦闘」。
強力な鬼に苦戦しながらも、次の展開を予感させる会心の一撃を与える「第二の転換期」。
そして「解決」は次話へ。
『鬼滅の刃』の原作はすでに終了しているものの、いまでもSNSでは様々な考察が行われている人気ぶりだ。
考察の内容を見ると、細部からも読み取れる深い設定があることを知って驚嘆するばかりだ。
主人公に限らないキャラクター設定の詳細さもすごい。
仲間にも鬼殺の剣士になった過去があり「喪失」が作中で語られている。
それが「行動原理」につながり、キャラ立ちし、ひとりひとりが主人公級に魅力あるキャラクターになっている。
サブキャラクターが中心のスピンオフ作品が作られるほどだ。
敵である鬼にも、同情してしまいそうな悲しい過去が丁寧に描かれている。
姿形や血気術と呼ばれる技には、人間の頃に失った大切な何かが反映されている。
鬼となり心すら「喪失」している敵は、倒される最期の一瞬だけ人の心を取り戻す。
追憶の中、自分が鬼になってしまったせいで回復できない「喪失」を自覚する。
後悔しながら塵となり消えていく描写に、読者は自然と考えさせられてしまう。
『鬼滅の刃』には、敵味方関係なくキャラクターの人生がしっかり設定され描かれている。
『鬼滅の刃』の人気要素は『クリエイターのための物語創作ノート』の内容と一致する。
このように超人気作品を振り返れば、本書の内容が真実であることがわかる。
本書の内容をマスターし実践すれば、あなたも多くの人に読まれ支持される物語を描くことができるはずだ。