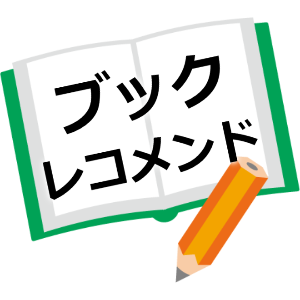はじめに:「人生を好転させたい」と感じる人へ
人生というゲームを攻略する最強のチートを手に入れる。
人生はつまらない――自己啓発本を買う人は「人生は楽しいもの」という前提がある。
それなのに自分はうまくいっていない。
だから成功法則を求める。
しかし、それは大きな間違いだ。
「人生なんてつまらない」
それが正解。
私たちは「つまらない人生」をおもしろくするためのゲームをやっている。
本を読むことで、人生というゲームの攻略法を知ることができる。
世界がどうなっているかを知らないとゲームは攻略できない。
本を読めば、世界の見え方が変わる。
本を読めば、あらゆることが好転する。
書籍の基本情報
| タイトル | : | 本を読む人はうまくいく |
| 発行日 | : | 2025年6月14日 |
| 著者 | : | 長倉 顕太 |
| 発行所 | : | すばる舎 |
| 詳細 | : | 本を読む人はうまくいく |
YouTube動画:ずんだもんと学ぶ!成功者の読書法
本書を参考に作成した、ずんだもんの動画をYouTubeにアップしました。
主要なポイント・学び
文化庁の調査によれば、日本人の6割超が「月に1冊も本を読まない」と回答している。
しかし、人生を好転させるためには読書以外の手段はない。
ここでは「人間関係構築能力」と「環境適応能力」を鍛える方法を学ぶことができる。
Q:本を読むとは、どういうことか?
A:本を読むとは「世界の地図を手に入れる」ということ。
初めに言があった――「ヨハネによる福音書」の冒頭にある言葉。
私たちが認知できるものは、すべて言葉で説明できる。
私たちにとって、世界は言葉しかない。
言葉とは知識――知識を得ることは世界の地図を手に入れることに等しい。
人生がおもしろくない人は、地図を持っていない。
または、ダマされてニセモノの地図を持っている。
正しい地図を持っていない人は、他人によって人生を決められていく。
読書とは、正しい地図を手に入れることである。
ニセモノの地図――私たちは学校教育で「答えは1つ」と教育される。
日本では、ゲームの攻略本がベストセラーになる。
答えを自分で探すのがゲームの楽しみであるはずなのに。
先に答えを知ることが快感になっている。
それほどまでに「答え中毒」になっている。
日本人は、何事にも1つの答えがあると考えてしまう。
しかし、人生において答えなんてない。
それなのに、答えが必ずあると考えて選択することができない。
大切なことは、選択することではなく、選択したものを良くすることだ。
それが、人生。
「答えは1つ」と洗脳されている人は、他人がつくった選択肢以上に視野を広げることができない。
世界は「情報」でできている――私たちは、五感から得る情報を処理しながら生きている。
うまく生きるためには、情報を的確に取得し、処理できなければならない。
しかし、多くの人はものを知らなすぎる。
だから、他人によって人生を支配されてしまう。
知らないから、そのことに気づくことすらできない。
知らない人は、視野が狭くチャンスが目の前にあっても気づかない。
人生の航路さえも変える力――読書には、その力がある。
本を読む習慣を持てば、知識を持つようになる。
知れば知るほど、知らないことに気づく。
知らないことを知りたくなり、視野がどんどん広がっていく。
そうすれば、チャンスをつかむことができる。
そのカギとなるのが本なのである。
Q:なぜ、本でなければならないのか?
A:読書は、コスパ・タイパが最強の方法。
なぜ本か?――読書は、コスパ・タイパが最強。
国債金融資本を支配するユダヤ人の教えは、知識に投資すること。
そのうえで、本は最も投資効率がいい。
旅行に行かなくても、ページをめくるだけで遠く離れた異国のことも知ることができる。
知識が増えれば悩みが減る。迷い悩んでいるムダな時間が消える。
決断が早くなり、すぐに行動に移ることができるようになる。
読解力が身につく――情報社会では、膨大な量の知識が文字により伝達されている。
あらゆるメディアの文章が知識の宝庫。
読解力がなければ、これらの知識を獲得することはできない。
自分の知識体系を更新し「自分の世界」を拡張していくための基盤になるのが読解力だ。
能動的である――読書は自分の視野を広げ、新しいアイデアを生む可能性を高める。
それは、積極的に「自分の世界」を構築する創造的なプロセスだと言える。
「自分の世界」を構築するとはどういうことか?
読書により、本の著者の主張に触れることで、自分の価値観を知ることができる。
たとえば、あなたはここで「人生には答えはない」という主張を知る。
自然と、それに対する「自分の思い」が湧き上がる。
肯定なのか、否定なのか、その思いこそが、あなたの価値観。
ときに、誰かに植え付けられた偽の価値観に気づくことができる。
読書は、新しい自分の価値観との出会いとなる。
Q:なぜ、あなたは本を読むことができないのか?
A:あなたが本を読めないのは、まわりの人間のせい。
私たちは、生まれてから誰かによってキャラクターを決められている。
誰かとは、親だったり、学校だったり、社会だったり、あなたを取り囲む人たち。
あなたは周りの人にとって都合のいいキャラクターにさせれられている。
まるで映画やドラマのエキストラだ。
それは、人生を決められていると言っても過言ではない。
もし、あなたが意志が弱いなら、それは誰かに意志の弱いキャラクターにされてしまったのだ。
「意志の弱い凡人」というキャラクターでいる限り、あなたは人生を変えることはできない。
身近な人は拒絶反応を示す――私たちの世界は、あらゆる人、モノの関係性で成り立っている。
その関係性を乱すことは周囲の人間にとって不快であるため、無意識に阻止しようと動く。
新しい挑戦は、周囲に「よけいなことを始めた」と映る。
「そんなのムリだ」
「やめておいたほうがいい」
特に親しい友人や家族が止めに入る。
あなたが、読書で人生を変えたいと思っても自然と邪魔してくる。
「その本にダマされているだけだ」
人は現状維持を求める生き物。
周囲の人は、ただ「通常」の反応を示しただけ。
彼らは、悪意を持ってそうしているわけではない。
Q:本を読むためには、どうすればいいのか?
A:本を読むためには、読書家のフリをするだけでいい。
難しい本を持ち歩く――あなたは周囲の人から難しい本を読む人間と見られる。
その結果、あなたは難しい本を読めるようになる。
「本を読む人」は、本を読むからなるのではない。
「本を読む人」になるから本を読めるのである。
あなたが読書ができない理由は、読者ができないキャラクターにされているからだ。
だが、他人に設定されたキャラクターで一生を終える必要はない。
あなたは、これからすぐにでも読書家になることができる。
Q:本を読むとどうなるのか?
A:「環境適応能力」と「人間関係を構築する能力」が身につく。
環境適応能力を高める――技術革新やグローバル化、価値観の多様化など。
環境はめまぐるしく変化し続ける。
環境に適応するためには、新たな情報を取り込み、自分自身をアップデートしていく必要がある。
人間は無意識に現状維持を望み、変化を嫌う。
しかし、それでは環境に適応できなくなっていく。
読書とは、他人の人生や思考プロセスを疑似体験することだ。
それは擬似的にさまざまな環境変化に触れ、対応策を考える習慣をつくり出す。
読書は、自分の経験や常識に縛られることなく、環境適応能力を高めるトレーニングになる。
人間関係の構築――読書とは、著者との対話である。
著者の考えを理解することは、読解力の向上。
読解力が上がれば、コミュニケーション能力が向上する。
相手の意図を正確に把握することは、良好な人間関係の構築に役立つ。
知識や経験が豊富なほど魅力的に映る。
人が惹かれるのは「自分が知らないことを知っている人」。
読書によって得た知識は、会話の質を高める。
読書は、人気者になる最短ルートだ。
職場の飲み会やプロジェクトにも必ず声がかかる。
呼ばれる機会が増えれば出会いも増える。
出会いが増えればチャンスも増える。
知識が価値ある人々を引き寄せる。
Q:おすすめの読書法は?
A:自分の専門外の本を積極的に読む。
一歩飛び出す読書――画期的なアイデアは「異文化の融合」から生まれる。
自分が慣れ親しんだ世界から飛び出し読書を続けていると、思いもよらない発見がある。
自分の行動の幅を広げるきっかけとなり、環境適応能力を格段に高めてくれる。
本を選ぶ際に、あえて自分が無関心なジャンルを手に取る。
好奇心は、生まれつきのものではない。
好奇心は訓練によって育てる。
人は無意識に「慣れ」を求め「やったことがないこと」を避ける。
しかし、この好き嫌いの価値観も過去に誰かに押しつけられたものだ。
開放されるためには「やったことがないこと」を選択していくべきだ。
A:「広く浅い」読書法。
完璧主義を捨てる――すべての本を深く読み込む必要はない。
「目次」「章の冒頭と末尾」「見出し」「太字部分」などを中心に全体像を素早く把握する。
「本の冒頭」「目次」「結論」を読むだけでも、本のおおまかな主張を把握できる。
そのために重要なことが、次の2つである。
- 完読にこだわらない。
- 「この本から何を得るか」という目的意識を持って読む。
必要に応じて深掘りするフレキシブルな読書姿勢が、現代社会では有用だ。
浅い理解でも会話のきっかけとなれば十分な価値がある。
知識を深めたければ、その会話の相手から学ぶことができる。
A:行動のための読書法。
人生は行動がすべて――インプットとアウトプットはセットで行うことが重要。
どんな本を読んでも、行動に移さなければ知識は頭の中に眠ったままだ。
読書で得た知識を活かし、実践の場をつくる。
小さな行動を繰り返し経験を積むことで環境適応能力は鍛えられていく。
読書は、多様な人間関係を構築・維持するための強力なツール。
多様なジャンルの知識に触れておくことで、どんな相手とも会話を始めるきっかけをつくれる。
社会ネットワーク理論の研究において「情報の架け橋」という概念がある。
広く浅くの知識の断片は、自分が異なる分野の人をつなぐハブとなることに役立つ。
そうなると、自然と多様なネットワークの中心にポジションを確立することになる。
読書はこのように「ゆるやかなつながり」を形成する。
それは、いざというとき頼れる強力なネットワークとなりレジリエンス(回復力)を高める。
まとめ・感想
AI時代の「頭の良さ」とは、「環境適応能力」と「人間関係を構築する能力」。
AIは、すべての人に対して高い知能を提供してくれる。
それでは、これからの時代の「頭の良さ」とは何だろうか?
これからの頭の良さは「人間関係をつくる能力」と「環境適応能力」。
この2つの能力は、読書で身につけることができる。
読書家になりたければ、読書家のフリをする。
では、読書をするためにはどうすればいいのだろうか?
それは、読書家のフリをすればいい。
私は、このブログを運営するにあたって、本を読む。
忙しかったり、疲れていたりで本を読む気分じゃないこともある。
でも「本の要約ブログをやっているキャラクター」だから本を読むことができる実感がある。
「引き寄せの法則」では、お金持ちになりたければ「お金持ちのフリをしなさい」と言われる。
正直、これは半信半疑だ。
しかし、読書家になりたければ「読書家のフリをしなさい」は、実践して確実に効果がある。
「フリをする」ことで、読書家にはなれて、お金持ちにはなれないと思うのは不思議だ。
「キャラクターが人生を決める」というのは、本当のことなんだと思う。
本書では、私たちは親が学校や社会が決めたキャラクターを演じていると言う。
それは「人生も決められてしまっている」ことに等しい。
『タフティ』では、それを「映画の登場人物」として表現している。
映画の支配から逃れるためには、目を覚まさなければならない。
読書を習慣にしていると、色々な本がつながっていく。
読書はおもしろい。
広く浅く、自分の専門外の本も読む。
本書のおすすめの読書法は「広く浅く」だ。
私の場合、好きな本ばかり選んで読んでしまっている。
たまには興味がない本でも読む必要性について知ることができた。
しかし、興味がない本を読むことは、普段の読書よりもハードルが高い。
おもしろく感じることができないかもしれない。
だからこそ「全部を読まなければならない」という完璧主義を捨てる必要がある。
「この本から何を得るか」という目的意識を持ち、完読にこだわらない。
私たちは無意識に「やったことがないこと」を避けてしまう。
読書は「やったことがないこと」を選択するためのトレーニングとして最適だ。
たとえ読書で失敗しても、誰にも迷惑をかけないし自分が傷つくこともない。
新しいことをやってみようと思う。