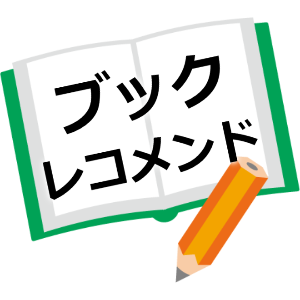はじめに:『ジャンプ』作品に夢中になった、かつての少年たちへ
この記事では、ジャンプ編集部で伝説を築いた鳥嶋和彦さんの著書「ボツ 『少年ジャンプ』伝説の編集長の“嫌われる”仕事術」の一部を要約しつつ、私自身の感想を交えて紹介する。
書籍の基本情報
| タイトル | : | ボツ 『少年ジャンプ』伝説の編集長の“嫌われる”仕事術 |
| 発行日 | : | 2025年5月22日 初版第1刷発行 2025年5月22日 電子書籍版発行 |
| 著者 | : | 鳥嶋和彦 |
| 発行所 | : | 小学館集英社プロダクション |
| 詳細 | : | ボツ 『少年ジャンプ』伝説の編集長の“嫌われる”仕事術 |
主要なポイント・学び
ボツーーこの言葉は作家にとって、この上ない無慈悲な響きだろう。
それでも著者は「ボツ」を出す。
当然、憎まれることを承知の上で。
それは、何故か?
本書では「“嫌われる”仕事術」を学ぶことができる。
次の内容は、本書の目次である。
目次を見るだけで、こんなにワクワクするビジネス書が他にあるだろうか?



ここでは、著者と鳥山明先生のエピソードの一部を紹介し感想を述べていく。
鳥山先生に才能があると思った理由
誰もが疑う余地のない鳥山先生の才能。
しかし、それは私たちが鳥山先生の作品を見て知っているからだ。
まだ何の実績もなく、技術も追い付いていない状況ならどうだろう?
それでも、著者が鳥山先生に「才能がある」と感じた理由は何だったのだろうか?
要約|原稿がきれいだった
鳥山先生は、『ジャンプ』の新人賞に応募したが落選。
しかし、その漫画を見た著者は「いいな」と思った。
鳥山先生の原稿がきれいだった。
修正の跡が一切なかった。
それはつまり、原稿が早く上がる。
そして、絵を上達させる時間がかからない。
鳥山先生にすぐに電報を打った。
君には才能がある。
感想|そして伝説へ
鳥山先生の作品は、多くの人の人生に影響を与えたことだろう。
私もそのうちの1人。
そして、その影響力は衰えることを知らない。
そんな作品の数々があったのも、この出会いがあったからこそ。
それは、著者が25歳、鳥山先生が23歳のとき。
著者が鳥山先生の才能を見出さなければ、この出会いはかなわなかった。
ドラゴンボールやドラクエは生まれなかった。
あなたの大好きな作品がどのようにして生み出されたのか。
そのとき、どのような問題が起きていたのか。
その問題をどうやって乗り越えることができたのか。
数々の作品作りに当事者として携わった著者だからこそ語れることがある。
本書を通して、読者である私たちは時を遡り数々の伝説のはじまりを知るのである。
“嫌われる”仕事術
伝説の編集長の“嫌われる”仕事術。
これは、タイトルにも使われる本書の重要な学び。
しかし、一般的に「ビジネスの相手に嫌われること」はマイナスでしかないはずだ。
その真意は何なのだろうか?
要約|ボツを500枚出すということ
当時、朝早く起きられない鳥山先生は勤めていたデザイン会社を辞めてしまっていた。
鳥山先生はお母さんから1日500円をもらって生活していた。
ただし、それが許されるのは2年間のみ。
だから、鳥山先生は2年のうちにデビューしなければならなかった。
鳥山先生は、『ワンダー・アイランド』でデビュー。
しかし、それから『Dr.スランプ』を生み出すまでの一年半。
著者は、鳥山先生の原稿500枚にボツを出し続ける。
感想|ボツは愛情表現
持っている才能に関わらず、誰の人生にも期限がある。
その中で訪れるいくつもの分岐点がある。
望んだ方向に進むためには「どれだけ夢中になれるか」が大事なんだと思う。
自分が心血を注いだ作品に「ボツ」を出されるのは、かなりきつい。
しかも500枚も。
当然、ボツを出す側もそれはわかっているはず。
それでもボツを出せる著者もスゴい。
鳥山先生は、後に「この1年間は勉強になっておもしろかった」と語っている。
自分が成長している手応えを感じていた。
相手のことを本当に思っているからこそ言える言葉がある。
本気でぶつかることができる。
嫌われそうなことでも相手のためなら愛を持って実行する。
これが“嫌われる”仕事術。
著者は、『Dr.スランプ』では、「Dr.マシリト」として登場。
『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 』では、「大魔導士 マトリフ」として登場している。
嫌う以上の愛情がなければ、漫画家は大切な作品に著者を登場させたりなどしないはずだ。
“嫌われる”仕事術は、ただ嫌われるだけではない。
マイナス以上のプラスを生み出す。
鳥山先生の漫画がピンと来なかった理由
500枚のボツを出されても、負けず嫌いな鳥山先生は漫画を描き続ける。
鳥山先生は、修正する中で確かに手応えを感じていった。
そうして『Dr.スランプ』が生み出される。
『Dr.スランプ』は、『ジャンプ』の読者アンケートで1位を取り、アニメ化も果たす。
『Dr.スランプ』は、これまでの鳥山先生の漫画と何が違ったのだろうか?
要約|キャラクターが確立していなかったから
著者は、鳥山先生が『Dr.スランプ』で、アラレを登場させてきたときに気付いた。
それまで鳥山先生の作った漫画がピンと来なかった理由。
それは、ストーリーのせいではない。
キャラクターが確立していなかったから。
『Dr.スランプ』では、自称天才科学者の則巻千兵衛が主人公だった。
しかし著者は、「アラレを主人公にしたほうがいい」と提言した。
ところが、鳥山先生は2話目にアラレを登場させなかった。
著者 :「えっ、アラレは?」
鳥山先生:「少年誌だから、女の子を主人公にしたくない。嫌だ」
著者は「自分が言っていることが正しい」ことを証明するために鳥山先生と賭けをする。
女の子を主人公にした読み切りを描いて、読者アンケートで3位以内ならアラレが主人公。
4位以下なら、鳥山先生が言うとおり、アラレの登場は1話だけ。
そういう賭けだ。
鳥山先生は『ギャル刑事トマト』を描き、その結果3位になった。
『Dr.スランプ』の主人公は、アラレになった。
感想|衝撃に続く衝撃
著者は、アラレの登場で衝撃を受けた様子だった。
ロボットなのに目が悪くてメガネをかけている。
女の子とおっさんの共同生活。
当時のジャンプは「友情・努力・勝利」をスローガンに掲げたハード路線の作品ばかりだった。
そんな中、女の子をかわいく出してあげることは武器になる。
そう確信した後、それを覆してくるとは著者も予想できなかっただろう。
衝撃に続く衝撃。
本書では、こんな笑い話のようなエピソードを知ることができるのも魅力の1つだ。
先輩や上司の意見をスルーする
当時の『ジャンプ』の漫画は「男はこうあるべき」という熱血ものばかりだった。
社内からの『Dr.スランプ』への反応は、著者の感覚とは真逆のものだった。
会社とは、チームで突き進んでいくもの。
しかし、先輩や上司の意見は、自分が面白いと思うものとは違う。
著者は、このときどうしたのだろうか?
要約|自分が好きじゃないものに合わせたら、毎日がつらいだけ
『Dr.スランプ』のネームを社内で見せたとき、不評だった。
早稲田の漫研を出た落語好きの先輩のデスクに次のように言われた。
「面白くない」
「ギャグ漫画なのに落ちがない」
「ダメだよ、こんなことやってちゃ」
しかし、著者はこう切り捨てる。
「その考えは古い」
漫画に大切なことは、話の完成度ではない。
漫画の連載はライブだ。
読者の大好きなキャラクターが何をしているのかが伝わればいい。
他の人は、自分を一生懸命『ジャンプ』に合わせようとする。
しかし、著者はそうしなかった。
何を言ったって、読者アンケートで上位を取れば勝ち。
その後、『Dr.スランプ』は3週目で読者アンケートで1位になった。
自分が好きじゃないものに合わせたら、毎日がつらいだけ。
感想|自分じゃなきゃできない仕事をやらないと意味がない
著者は次のように語っている。
「自分がワクワクドキドキしないものは面白くない。」
「自分じゃなきゃできない仕事をやらないと意味がない」
著者は何でもないことのように語っているが、そう言えるのはスゴいことだ。
相応の実力がなければ自分を貫くことはできない。
多くの人は、それができず同調圧力に負けてしまう。
文句を言いながら、現状に甘んじて生きている。
しかし、人生には期限がある。
面白くないことをしていて本当に良いのだろうか?
これは、楽をしようという意味ではない。
自分が面白いと思うことをしよう。
『ドラゴンボール』が生まれた理由
『Dr.スランプ』の連載がはじまり、読者アンケートでも1位を取ることができた。
そこから順調に進むかと思われたが、残念ながらそうならなかった。
鳥山先生は、連載が辛くなってきた。
しかし、『ジャンプ』が『Dr.スランプ』をやめることを許すわけがない。
著者と鳥山先生は、どうやってこのピンチを乗り越えたのだろうか?
要約|『Dr.スランプ』より面白い連載が作れたら、やめてもいいよ
『Dr.スランプ』の連載が始まって半年が経った頃。
鳥山先生はこう言い出した。
「連載をやめたい」
1話完結の15ページの週刊連載は、本当につらいものだった。
話を作るのに3日。
それから、原稿を2日で完成させる。
もし、修正指示があれば、一話をほとんど全部書き直さなければならない。
しかし、人気が爆発してる『Dr.スランプ』をやめられるはずはなかった。
どうすればやめられるか?
「『Dr.スランプ』より面白い連載が作れたら、やめてもいいよ」
それが、当時の副編集長が出した条件。
それは『Dr.スランプ』をやめることを諦めさせるために出されたものだった。
そう思っていても著者と鳥山先生は『Dr.スランプ』を超える作品作りに動き出した。
『Dr.スランプ』を連載をしながら並行して読み切り作品を描いていった。
1年間繰り返し、反響を見ながらテストした。
しかし、どれも全くウケなかった
著者はある日、鳥山先生がジャッキー・チェンのカンフー映画が好きなことを知った。
鳥山先生は、画面を見なくてもセリフだけでシーンが分かるほど何回も繰り返し見ていた。
この話がきっかけだった。
「カンフーの漫画を一度描いてみてよ」
著者は、鳥山先生にそう頼んだ。
そうして出来上がったのが『騎竜少年』(ドラゴンボーイ)。
この漫画が後に『ドラゴンボール』の原型となる。
苦しみながら続けた『Dr.スランプ』の連載をやめる見通しが立った。
『Dr.スランプ』は、4年8カ月で連載を終えることができた。
感想|「得意 × 好き」
「ピンチはチャンス」という言葉があるが、私は好きではない。
ピンチはピンチだし、チャンスはチャンスだ。
ピンチなときは、ピンチをピンチだと受け入れて死に物狂いで覆すしかない。
鳥山先生が4年8カ月もかけてピンチを覆した方法。
それが、「得意 × 好き」。
鳥山先生の場合は「漫画 × ジャッキーチェン」。
鳥山先生は、「好き」で「得意」な「漫画」に「 ジャッキーチェン」という「好き」を重ねた。
それは鬼に金棒。
それができたのは、著者の視点があったからだ。
2人の協働がなければ『ドラゴンボール』は生まれていなかった。
分析と対策をするのが編集者の仕事
ピンチを乗り越えて始まった『ドラゴンボール』。
そこから順調に進むかと思われたが、残念ながらそうならなかった。
人気があまり出ない。
『ドラゴンボール』は、ドラゴンボールを7個集めていくストーリー。
ドラゴンボールを7個集めれば、どんな願いもかなえることができるという設定だ。
著者も「これはストーリーを作りやすくなる、すごいアイデアだ」と思った。
しかし、デメリットがあった。
著者も鳥山先生も、この状況になるまで、そのデメリットに気づくことができなかった。
ドラゴンボールを7個集めなければ途中でストーリーを切ることができない。
人気のない話でも省略することができないのだ。
要約|成功者のいいところは盗み、持っていないところを攻める
『ドラゴンボール』は、連載20本中10位を割るくらいまで人気が落ちてしまった。
打ち切りまであとわずかという状況。
何故、人気が出ないのか?
著者は、鳥山先生と毎日電話でディスカッションした。
そして、結論は出た。
悟空にキャラクターとしての魅力がない。
子どもたちに「悟空は何をやりたいキャラなのか?」を印象付けられていない。
著者 :「悟空っていったい何をやりたいキャラなんだろうね?」
鳥山先生:「やっぱり、”強くなりたい”ってことじゃないかな」
キャラクターが魅力的な漫画は人気が出る。
漫画を描くのが漫画家の仕事。
そして、分析と対策をするのは編集者の仕事だ。
1位の漫画には、読者が好きな要素が詰め込まれている。
著者は、人気1位の『北斗の拳』を徹底的に研究した。
作画の原哲夫先生の絵は、一枚絵を描くのはうまいが連続アクションは得意ではない。
そこで「秘孔を突く」という演出をしている。
止め絵の連続を使って描くことで絵の良さを生かしながら絵の弱点を補っている。
成功者のいいところは盗み、持っていないところを攻める。
原先生に勝てるのは、鳥山先生の絵が持つ「動きの自由自在なアングル取り」だ。
2人の協働により『ドラゴンボール』の人気を一気に上げる。
そのための施策が2つ。
- 悟空を修行させて、それを成果で見せる。
- 「2Dを3Dに見せる力」と「連続する動きのスピード感」で魅せる空中戦。
この2つを披露できる場として「天下一武道会」という舞台が設定された。
感想|「得意 × 好き × 得意」
理由がわかっている問題は、問題ではない。
その理由を突き止めて改善策を見つければいいだけだ。
必要なことは、第三者視点での分析と対策。
成功しているものを徹底的に研究する。
成功している要素を見つけて、それを自分の得意な方向にずらす。
1位の『北斗の拳』は、原先生の絵の持ち味をうまく活かしている。
成功している要素は「絵の持ち味を活かす」。
それなら、「鳥山先生も絵の良さをもっと活かせばいい」。
原先生の絵の良さをマネるのではなく、鳥山先生だからできる表現力をより発揮する。
そして辿り着いた新しい魅せ方。
「得意 × 好き」に対して、さらに絵の良さを活かした「得意」を重ね掛けする。
つまり、「得意 × 好き × 得意」。
「フリーザ編」で終わらせるべきだった
『ドラゴンボール』で最も盛り上がったのが「フリーザ編」。
著者は、きれいに終わるならここだったと言う。
それなら、どうしてそうできなかったのだろうか?
要約|もしそこで終わっていれば、新しい作品を作れた
「描いていて楽しくない」
鳥山先生は苦しんでいた。
それでも『ドラゴンボール』は終わらなかった。
それは何故か?
当時の編集長がそれを許さなかった。
『ドラゴンボール』は人気がありすぎたのだ。
そして、著者は「Vジャンプ」を創刊して、既に「ジャンプ」編集部を出ていた。
いくら初代担当だからって「『ドラゴンボール』を終わらせてください」とは言えない。
言ったら大変な騒ぎになっていた。
しかし、著者はそれでも何かできたのではないかと後悔している。
もしそこで終わっていたのなら。
鳥山先生は、もう一作、新しい作品を作れていただろう。
感想|『ドラゴンボール』からは何も学べない
ドラゴンボールを無理に引き延ばしていなければ、鳥山先生はどんな漫画を描いていただろう?
つい思いを馳せてしまう。
読んでみたい。
でも、もう読むことは出来ない。
誰の人生にも期限がある。
著者は、ドラゴンボールは「フリーザ編」で終わらせるべきだったと言う。
しかし、私の中では「魔人ブウ編」の最後の闘いが最高だった。
誰と合体するかで戦況が大きく変わるという途中の展開はイマイチだったけど。
その流れを悟空が変えた。
「自分ひとりの力だけで闘いたいんだ。」
そこから最後の超特大の元気玉を決めるまでの経緯が激アツすぎた。
著者は「『ドラゴンボール』からは何も学べない」と言う。
炭酸飲料やミントガムと一緒で、一瞬爽やかになれれば十分。
スカッとして終わり。だからいいんだ……と。
そう言われると、そうかもしれないと思った。
漫画を読んでいる間、嫌なことはすべて忘れることができる。
そういう時間があるからこそ、乗り越えられたことが人生にはある気がする。
頭カラッポの方が夢を詰め込める。
漫画から何かを学びとろうとするより、純粋に物語を楽しむ。
それが正しい漫画の読み方かもしれない。
それに、本当に面白い漫画を読んでいると自然とそうなる。
「魔人ブウ編」の最後のクライマックスはとても感動した。
いまでも思い出し、その瞬間の感情を呼び起こすことができる。
鳥山先生、辛くても『ドラゴンボール』を描き続けてくれてありがとうございます。
YouTube動画:ずんだもんと学ぶ!『ボツ』の仕事術
本書を参考に作成した、ずんだもんの動画をYouTubeにアップしました。
総まとめ
この記事では、著者と鳥山先生のエピソードを要約し紹介した。
しかしそれは、ほんの一部に過ぎない。
他にも面白いエピソードは数多く掲載されている。
有名脚本家が書いたアニメの『Dr.スランプ』の脚本がまったく原作に準拠しなくて大失敗した話。
鳥山先生が『ドラクエ』のキャラデザインをすることになった理由。
『Dr.スランプ』のアニメ化で得た教訓を「ドラゴンボール」のアニメ化で活かした話。
アニメのタイトルが途中で『ドラゴンボール』から『ドラゴンボールZ』に変わった理由など。
つい誰かに話したくなる内容が満載だ。
もちろん、鳥山先生にまつわる話だけではない。
本書では、岸本斉史先生の『NARUTO-ナルト-』、久保帯人先生の『BLEACH』、冨樫義博先生の『HUNTER×HUNTER』等の超ヒット作品にも触れていく。
また後半では、尾田栄一郎先生の超人気作品『ONE PIECE』が新連載会議で3度も落ちた理由。
そして、『ONE PIECE』の連載を決断した理由が語られる。
それから『ONE PIECE』を通して編集部と担当編集のあり方へと深い話に発展していく。
「作家の意思を優先します」という編集者は逃げていると著者は言う。
才能があるということは稀有なこと。
才能には敬意と観察力を持って接しなければならない。
著者の言葉は、すべて著者がメガヒットを連発できる理由に通ずる。
それらの発言を含め、すべてをまとめて一言で表現したのが「“嫌われる”仕事術」なんだと思う。
「“嫌われる”仕事術」とは、自分のためにする仕事の仕方ではない。
大切なことは、本当に向き合うべき相手のことを常に考え、ブレない姿勢。
だからこそ、血と汗の結晶でもある原稿500枚にも妥協せずにボツを出すことができる。
本当に向き合うべき相手のためなら、自分が誰に嫌われることを厭わない。
それが「“嫌われる”仕事術」。
そして「“嫌われる”仕事術」は、嫌われはするけど、嫌われるだけじゃない。
その真意は、伝わる相手にはちゃんと伝わる。
多くの超人気作品登場の裏側には、「“嫌われる”仕事術」があった。
本書を読んで「“嫌われる”仕事術」を学ぶとともに、ぜひ『ジャンプ』作品に夢中になったときのワクワクドキドキを思い出して欲しい。